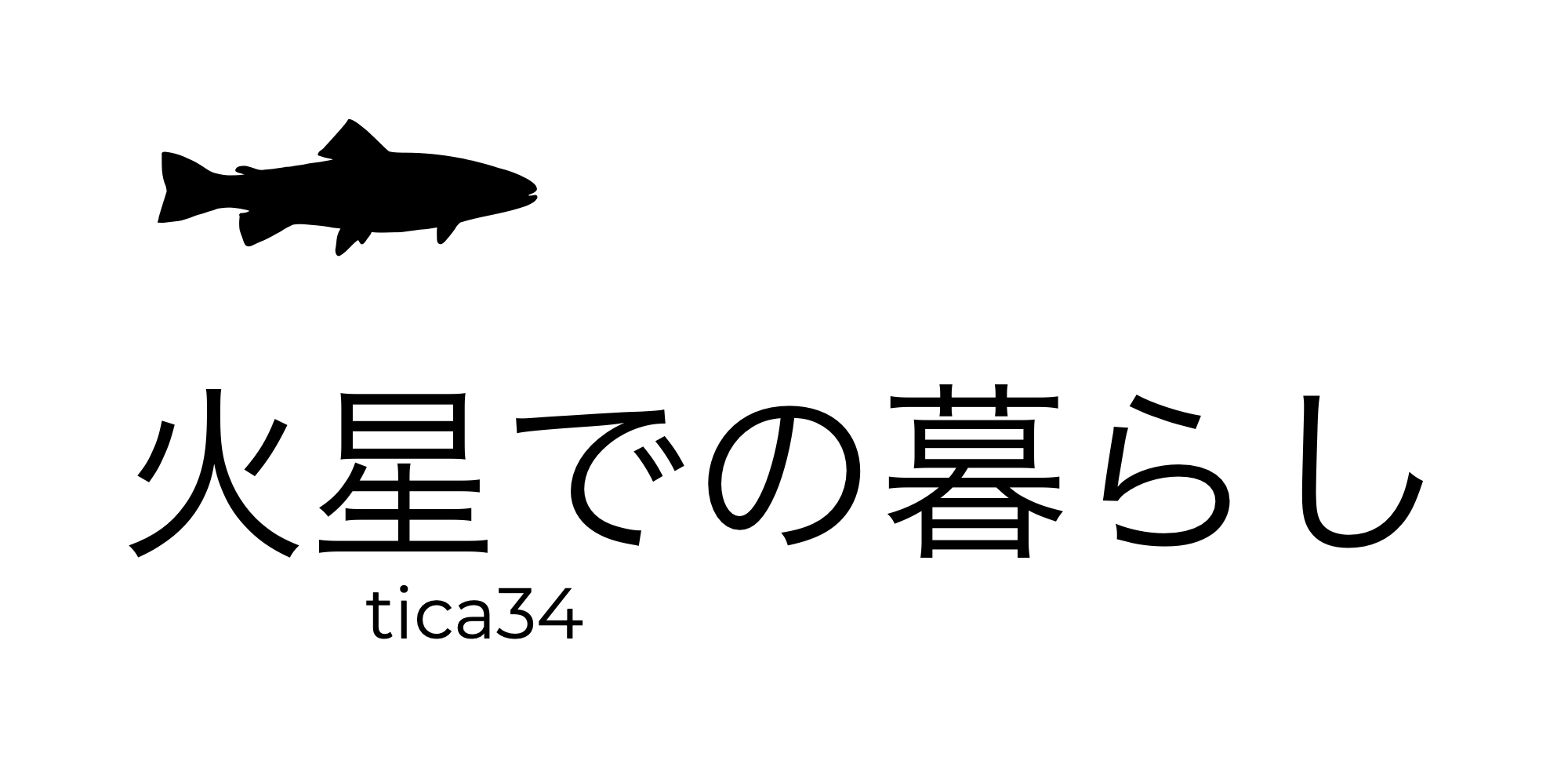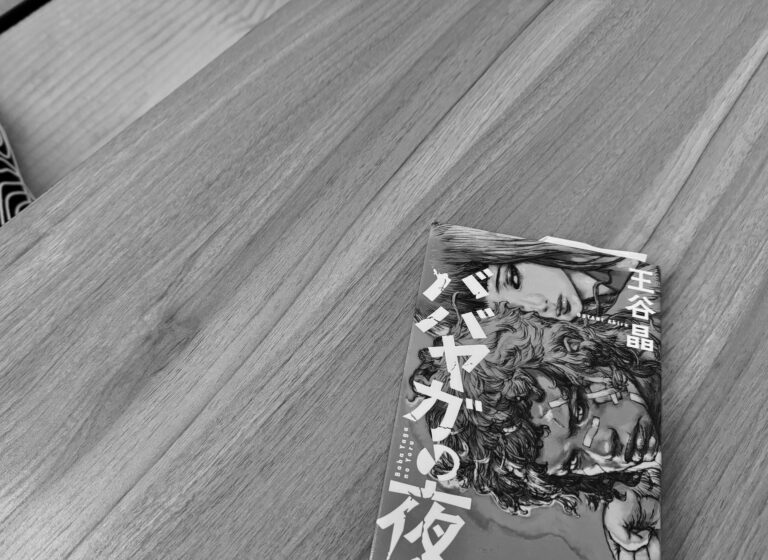8月が終わった。
ことしは特別に暑い、とあちこちから聞こえていた気がする。けど、そんなことを毎年言っている気がする。じつは高校野球もここ3年ほどは球場で観戦することができなくなっているし(近年は中継も充実してきているのもある)、きっと毎年のように特別な夏が更新され続けているんだろう。
その8月は、試験勉強にかかりきりだった。
わたしは金融系の会社に勤めており、強制で取得しなければならない資格、のようなものがいくつかある。が、もとは派遣社員として入社したこともあり、強制力が非正規まで及んでいないのを(推奨、というこれもなかなか強めのワードで縛られてはいた)いいことに、わたしは逃げた。
そうして、逃げ続けることができなくなった、46歳。
その試験を『生命保険講座』といい、そのうちの9月にある試験が8科目の試験のなかで難関と言われる【生命保険計理】だった。
経理、じゃないのがミソだなと思うところで、その名前のとおりとにかく計算、計算、計算。
日頃の業務で電卓を使ったりすることはなくはないものの、この試験にはそれの比ではない「何々の何乗」やら、「2分の1分の何々」……やら、難解な計算がうじゃうじゃ出てくる。そんなのはもう無理。無理に決まっている。学生時代ですら数学はテストで40点とるのがやっとだったくらい苦手だったのだ。教師がいて、本業として勉強をしていてそんなだったのだから、仕事をしながら独学でそれをやれなんて尚更無理。さらには、もう入社した時から若ささえ失っており頭の柔らかさも変わっている。
けれど、非正規から正社員になったことは引いた視点で考えれば(特段スキルがあるわけでもなく、年も食ってる人間からすれば)ありがたい話だ。給料の水準は未だ残念なもんだとしても、その残念な給料をも支えなきゃならないからこその「必須」なのだ。
ああ、世知辛い。
ともかく、やるしかない、ということで8月は必死で勉強していた。
もう少しくらいは両立できるものかと思っていたけど、8月のあいだはほんとうに映画を観る時間もなかったし、週末にモーニングを食べに出かけることもできなかった(電卓やらを持って出かけるのが面倒だというのと、外で勉強が意外と集中できなかったため、断念)。
テストの合否はまだもう少し先。手応えについては何とも言えないけれど、もし「落ちた」となると来年再挑戦となり、そのことを考えると目眩がする。何とか通っていてくれと祈りつつ、9月の残暑を自由に過ごしている。
それはそうと計理。
計算問題のひとつとして「複利計算」がある。「5年で100万円ほしい場合、年利7%でいけるとして手元に幾らあればいいか」というような計算をするんだけど、問題を他人事のように解きながら「お金ってそういうふうに増えていくもんなんだな……」みたいなことをぼんやり考えた。
金融リテラシーを育てることなく46歳になっているわけだけれど、たとえばもっと若い時に「年利何%」みたいな世界と接していたら……。
8月はほとんど何もできなかった、と言いつつ、読書のほうは隙間時間を利用して王谷晶『ババガヤの夜』を読んだ。
少しずつ自分の過ごし方を取り戻していきたいところだが、秋から冬に向かっても試験は続いていく。ひとまず、次の科目は今回の計理ほどではない。取り戻しつつ、次(たぶん12月)の難関科目【会計】に備えたいと思う。
この試験は本来、新入社員のぴちぴち22、3歳が受ける試験。それを40もとうに過ぎた中年にいきなり課してくるって、まったくほんとうに、世知辛い。
きょうの本
王谷 晶:『ババガヤの夜』
日本人としてはじめて権威あるイギリスのミステリー賞であるタガー賞を受賞した同作。
武道の達人(柔道何段、とかではなく山で猛獣と戦うようなフリーの)に育てられ、自身も達人となった22歳の女性が主人公。面倒事からヤクザの事務所で用心棒をすることとなり、そこで組のひとり娘と出会う。
氏が受賞インタビューで語っていた「ミステリーとして書いたつもりはない」のとおり、ほんとにこのとおりの言ってみればヤクザ小説。
にもかかわらず、ミステリーの権威ある賞を受賞とはどういうことか……というのがこの小説の読みどころ。終盤にあっ、と声が出てしまう仕掛けがある。
これがミステリー賞とはじつにイギリスらしい。
作品は押しつけがましい表現はないライトな筆致なれど、登場する会話はいちいちウィットに富んでいておしゃれ。作中ではマイノリティの哀悲といった社会派的なことが語られる場面もあるんだけど、そういった尖りや蘞味は作品の純粋なおもしろさに溶け込んでしまっている。
まさに新感覚ミステリーといった感じの傑作。