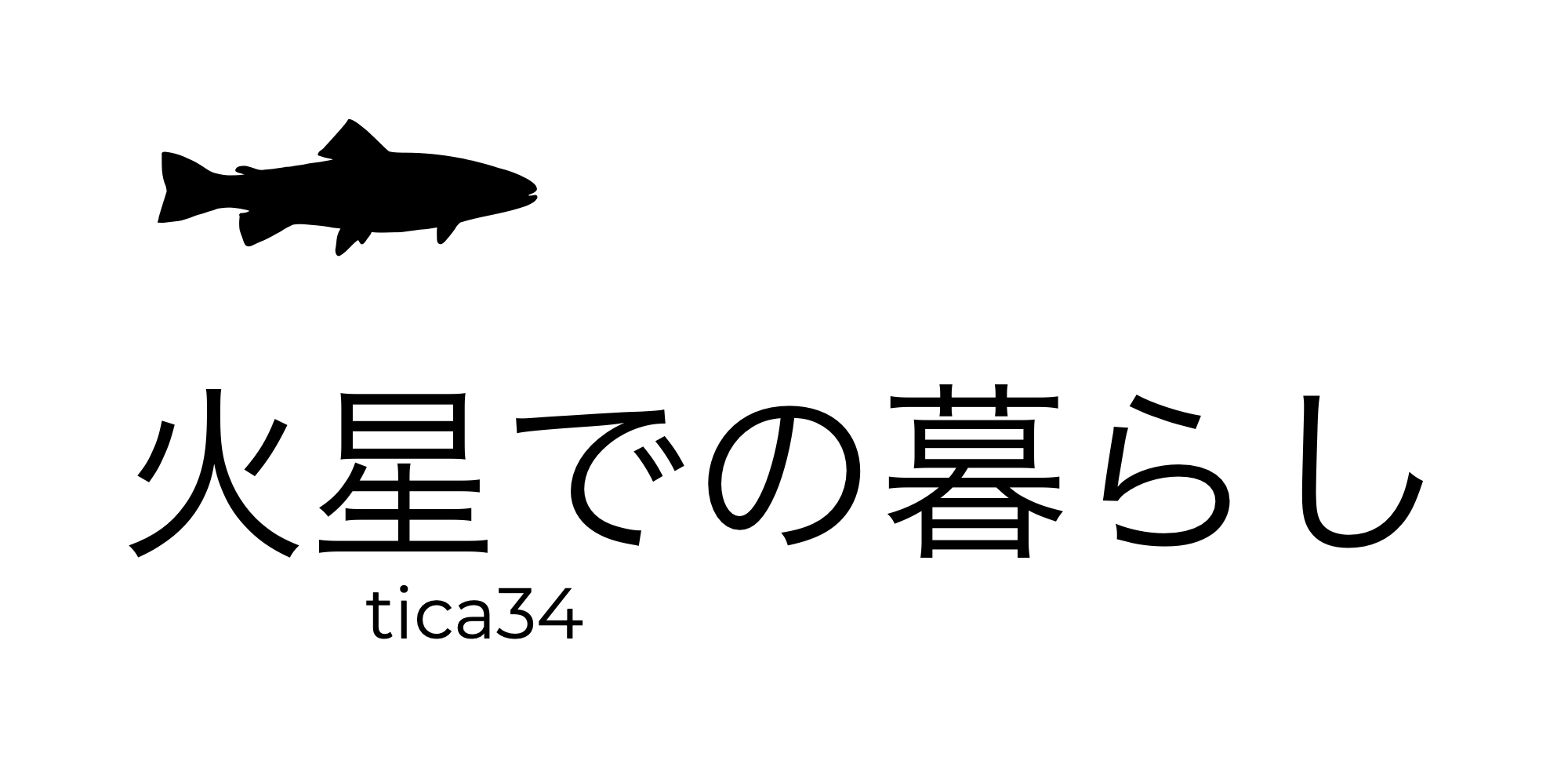酒をやめなきゃいけないのかもしれない、ということを考えはじめた日(つまり、ケーサツ屋さんにお泊まりした日)から酒を飲む機械が一度だけあったのだが、そこはいわゆる「リラプス(再飲酒)」の引き金にはならなかった。飲んだのはグラスに2杯のビール。ふつうにものすごく美味しかった。けど、それが呼び水になることはなく、その後はまた飲まない日々が続いている。
そこで、きょうは現在までの「酒をやめてみての体感」を正直なところで記してみたいと思う。
悪かったこと
1 旅先でどう過ごすのか見当がつかない
旅先でひとり、少し勇気を出して現地の酒場に入ってみる。それが楽しみだった。それがなくなるとしたら。(酒場以外の)観光地に出向くこともあまり興味がないし、アクティビティなんてもってのほか。
行ってみれば新しい習慣が身につくかもしれないし、もしくは旅先では限定的にお酒を楽しむことにしよう、となるかもしれない。実際に行ってみてどうなるか。
2 食事に合わせる飲みものがわからない
家で晩酌するのであればいい(酒はやめても、週末の晩酌の習慣はなくなっていない)。ノンアルビールかウィルキンソンの炭酸水にレモンを搾る。ライムでもいい。そういうカスタマイズがいくらでも可能。
けれど、たとえば野球場。大好きなピザやもつ煮込み、串焼きや揚げたてのフライに何を合わせる? コーラは好きだけど(個人的に甘い飲みものは)食事には合わないし、ウーロン茶っていうのもなんか……
お酒がもともと飲めないひとたちは野球場でどう過ごしているんだろう。
とくに変わらなかったこと
1 体調
体調は厳密に言えば「よかったこと」に入るんだけど、たとえば酔わない程度に飲んだ場合。ビールをグラスに2杯程度がわたしのそれに相応する適量で、それを飲んだ体感と、まったくのシラフだった時の体感はほとんど変わらない、気がする。
よくなったこと
1 体調
矛盾するようだけど、週末の体調はかなり軽やかになった。土曜の朝も日曜の朝も、二日酔いってほどではないけれど、爽快というにはほど遠い。わたしの週末の多くがそんな感じだった。
ちなみに、ケーサツ屋お泊まりの1週間後くらいに「入浴」がテーマの座談会に出席した機会があった。それが「酒をやめてもいいかも」という思いつきの背中を押すきっかけになったひとつだったのだけど、さまざまな効能のいい香りの入浴剤を紹介され、「ああ、金曜の夜は酒を飲まずにゆっくりスペシャルな入浴をして、ルイボスティーなんかを飲みながらゆっくり映画を観るのもいいかもしれない」と、シラフの夜を「いいもの」として捉える気持ちに傾いていった。
そして、実際にシラフの夜はよかった。
2 食欲のコントロールが容易になった
よく語られるところで、「酒を飲むと食べ過ぎる」というのがある。それはそうなんだけど、それ以上に飲酒の習慣によって「満腹中枢がバカになっていた」かもしれないと感じるところがある。飲んでいるその時に食べ過ぎるというのは当たり前として、それ以外の時であってもわたしはよく食べた。それが、徐々にだがわりと適切に箸を置けるようになってきた。
「おなかいっぱい」が少しわかってきた。
飲酒とは何なのか。
たくさんの禁酒本を読んでみたけれど、多くの著者はお酒に関しても飲むことに関してもクッソミソに断罪していて、実際頷けることも多いのだけど、実際自分が禁酒をしてみて、そこまで酒を断罪すべきなのかはわからないというのが正直な気持ちだ。
一方、川上未映子の小説『すべて真夜中の恋人たち』にアルコール依存症の女性が出てきて、実際依存症である、と作中で語られるわけではないんだけれど、主人公の女性(コミュ障)が意中の男性とコミュニケーションをとるためにどんどん酒に溺れていく。
リアリティというよりはすごく特殊な依存だけど、それでも、いま現在のわたしの「ビールを2杯飲むことがいったい何だと言うんだ?」という正直な気持ちがたとえばそういう状態に繋がっていたり、ケーサツ屋の牢屋に繋がっていたりする。
そこは、忘れずにおりたいと思う。
きょうの本
川上未映子:『すべて真夜中の恋人たち』
<真夜中は、なぜこんなにもきれいなんだろうと思う。それは、きっと、真夜中には世界が半分になるからですよ>
小説内のこんな一文がイントロダクションに採用されていた。詩的で甘い、それでいて、バッサリ一線あるような独特の川上未映子ワールド。
揺るがすことのできない恋愛小説なんだけど、わたしは本文で書いたアルコール依存のくだりや、主人公が一日の仕事を終えてレトルトのソースをかけたパスタを食べ、熱いシャワーを浴びるみたいな日常のごく自然な描写がすごく印象に残っていた。
そういう細部が丁寧に描かれている小説は当たりであることが多い。
あるレビューサイトには「つまらなかったが、泣けた」とあって、何となくよくわかると思った。
そういう、(口に合わないと感じたとしても)とても印象深い小説だったのだ。