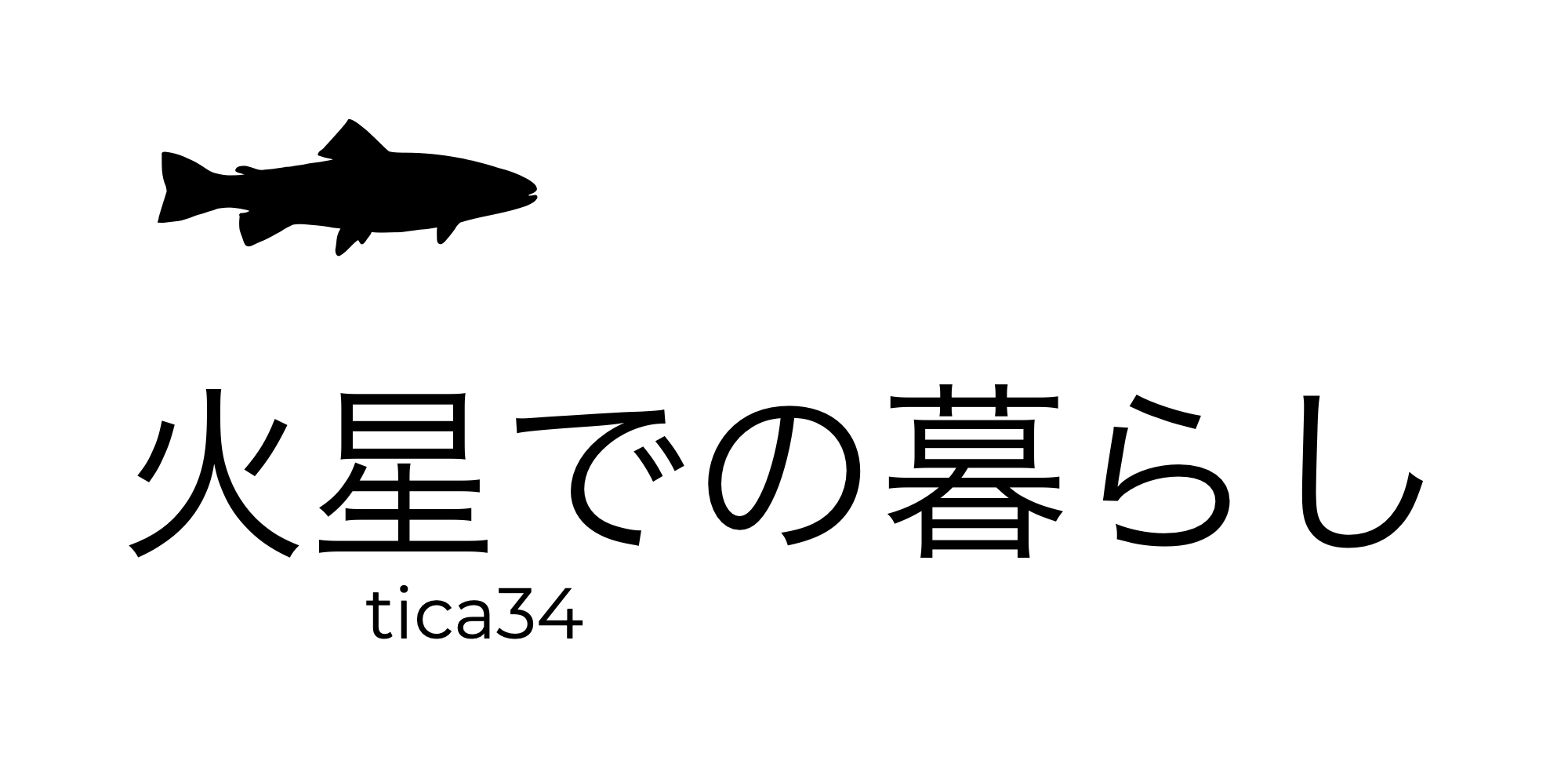村上春樹は贔屓にしているヤクルトスワローズの試合を観るために、日本で新居を探す際の条件を
「神宮球場へ徒歩で行けること」
としているらしい。
野球、ウィスキー、ランニング……村上春樹を構成するアイテムはいつだってオシャレだ。
というわけで今回は野球の話。
わたしは野球が好きだ。
といっても、そのきっかけは春樹のようにNPB球団のファンになったというものではなく(春樹と野球の出会いの詳細は知らないので、はじめの邂逅がスワローズだったのかはわからないが)、最初は高校野球だった。
というよりも、夏の甲子園。
金属バットの音、サイレンの響き。それからウグイス嬢の「~君」付けのアナウンス(何だかイントネーションも独特でゾクゾクした)や、ブラスバンドの応援。
子どものわたしにとっての野球とは、最初は単純に耳に心地のいい音の集合体だった。
「音」という意味合いとしてはもうひとつ。
記憶はおぼろげであるものの、耳についた「ウチュウカン」という奇妙な響き。宇宙。野球のなかにある宇宙とは。謎すぎた。
意味がわかってからは、「右中間」だとか、「適時打」だとか「併殺」だとか、そういう野球単語を好きになった。
ところで、野球用語をいちいち日本語に置き換えたのは、明治の俳人である正岡子規だとのことだが、SSの和訳である「遊撃手」だけは違うらしい。
訳したのは明治の教育者・中馬庚(ちゅうまかのえ)。
ベースボールを「野球」と訳したのもこの人物らしい。なんというセンス。
そういうわけなので、「子どものころから野球が好き」と言っても、野球そのものが好きというよりはそれに付随する絵的なもの。音楽や本の好きになり方と似ていたと思う。
そんなわたしがある時運命の選手に出会う。
高校野球(ここでいう「高校野球」とはつまり甲子園大会)を毎シーズン観ていると、時には特定の高校にフォーカスして観入ったり、また時には選手の名前を覚えたりすることもある。自分の出身県が勝ち進んだりすると尚更注目したりすることもあり、音と文字を好んでいても子どもの時分のルールも何もわからなかったころから比べると、それなりに大人になってからはだんだんと野球そのものを楽しむようにもなっていた。
それでも、選手が高校野球を引退すると毎年毎年きれいさっぱり忘れてしまう。どんな選手であったかも、その後の進路についても。数年後に話がぱっと出て「ああ! いたなあ!」と思い出したりすることはあっても、それ以上の存在になることはない。
そういうわたしが出会った、当時高校2年生のある選手。二塁からサインを読んで渋い三盗をしたり、流し打ちでライン際に二塁打を放ったり、とにかく渋い選手だった。目立っていたが、渋い選手だった。勝ち進むごとに気に入り、3年生で引退するころには「この選手とだけは高校野球でさよならできない」とまでになっていた。
その後、月日を経て彼はプロ野球選手になった。プロ志望届を出した、と報道されるや毎日気が気でなく、ドラフト会議の日は仕事にならないと有給をとった。
晴れて指名がかかり、「彼がドラフトされた球団のファンになる」と誓ってドラフト会議を見守っていたわたしはそうやってNPB球団のファンになり、もうそろそろ10年近くになる。
といっても、自分にいわゆる「プロ野球」が染みついたのかどうかは、よくわからない。
子どものころに惹かれた野球。
わたしはいまでも当時の、音や文字がとにかく好もしかったころのぼんやりした野球が好きだし、大人になってからは高校野球以外のアマ野球も観戦の機会があれば出かけたりと、「野球」というゲームそのものも好きにもなった。
ただ、プロ野球関しては10年近く経ったいまでも何となくその文化が自分事にならない感覚がある。応援歌も覚えないし、外野席にも行かない。子どものころに惹かれた野球のきらめきとは何か違う。と、思いながら、ただ運命の選手を追いかけるために、きょうもプロ野球に歩調を合わせているのである。

きょうの本
城井 睦夫:『野球の名付け親・中馬庚伝』
1988年11月にベースボール・マガジン社から出版。中馬庚が「野球」という言葉の名付け親であることを証明する研究成果を踏まえ、草創期の野球を解説しています、とのこと(AIより)。
野球の書籍を読むのは好きで、田尻賢誉の機動破壊シリーズとか読んで高校野球の戦術みたいなものにすごくのめり込んでいた時期があったのだけど、これはベースボールが「野球」となっていく歴史を示した本。
プロ野球を観るようになってからは、野球の本を読む時間は減ったように感じる。スコアも、いちおうつけられるけど、最近はつけていない。
代わるように視界に入ってきた言葉が「セイバーメトリクス」とか、「パークファクター」とか。このあたりもきちんと勉強したらもっと野球がおもしろくなるかもしれない。